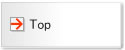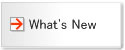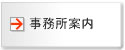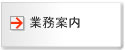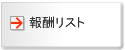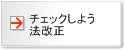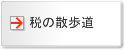令和7年度税制改正
1 法人税
(1)中小企業者等の法人税の軽減税率の延長
中小企業者の法人税率は、適用期限が2年間延長されます。 令和9年3月31日までのに間開始する事業年度に適用されます。
(2)防衛特別法人税の創設 法人税率は変えず、法人税額から年500万円の税額を控除をしたうえで、4%の「付加税」が課されます。 令和8年4月1日以後に開始する事業年度に適用されます。
2 所得税
(1)給与所得控除の最低保証額の引上げ 55万円から65万円に引上げられます。
(2)基礎控除の引上げ 合計所得金額が2350万円以下である控除額が所得階層ごとの控除額となります。2350万円以下の場合の控除額は、95万円から58万円となります。
(3)所得控除の対象となる合計所得金額定の引上げ 58万円以下となります。
(4)特定親族特別控除の創設 19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得が58万円を超えても123万円以下であれば特定親族が63万円から3万円までの控除が受けられます。
(5)(1)から(4)の適用 令和7年分以後の所得税に適用されます。